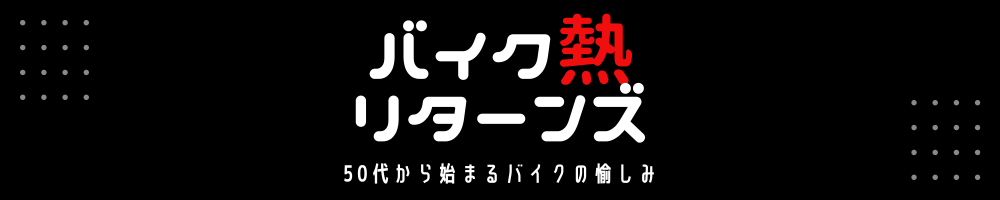(本ページにはプロモーションが含まれています)
1.イントロダクション
ホンダグロムは、小排気量ながらスタイリッシュなデザインと扱いやすさから、多くのライダーに支持されている人気モデルです。しかし、実際の燃費はどのくらいなのか、長期にわたる使用でのコストはどのように変化するのか気になる方も多いでしょう。特に、かつてバイクを楽しんでいたものの家庭や仕事の都合で一度降りた方が、50代以上になって再びバイクライフを始めるにあたり、維持費や燃費効率は大きな関心事ではないでしょうか。この記事では、燃費視点からグロムの魅力と長期使用時のコスト効果を徹底解説し、具体的な解決策や楽しみ方を提案します。
2.ホンダグロムの燃費性能の魅力

2−1.グロム燃費の実際の数値は?
ホンダグロムは小排気量ながらも実用性に優れ、燃費性能においても高い評価を受けています。実際、ホンダ公式サイトによると、グロムのWMTCモード値はおおむね60km/L前後とされています。ただし、実際に街乗りやツーリングでの使用となると、信号や渋滞、走り方の違いなどによって燃費は変動します。オーナーの口コミや__みんカラ__などのユーザー投稿を見ると、一般的にはリッターあたり50〜55km前後で推移している例が多く、燃費の良さが実感できるという声が多数あります。
燃費が良い要因としては、低排気量エンジンの燃料消費が少ないことに加え、グロム独特の軽量ボディによる負荷軽減も挙げられます。また、メーカー独自のPGM-FI(プログラムド・フューエル・インジェクション)技術によって、理想的な燃料供給を行い、燃費性能を最適化している点も見逃せません。これらの要素が相まって、グロムは「コストパフォーマンスに優れた遊べるバイク」として多くのライダーに支持されています。
2−2.燃費向上のための走行ポイント
燃費をさらに高めるためには、日々のライディングスタイルやメンテナンスが重要です。まず、発進加速の際に急激にアクセルを開けないこと。緩やかなアクセルワークを心がけるだけで、燃料の消費量を抑えられます。また、適切なギア選択も大切です。エンジンの回転数を無駄に上げすぎないようシフトアップを早めに行い、低回転域を有効に使うことで燃費を向上させることができます。
さらに、タイヤ空気圧のチェックは見落としがちなポイントです。空気圧が適正値よりも低い場合、路面との摩擦抵抗が増加し、燃費悪化につながります。取扱説明書や__ホンダ公式整備情報__を参考に定期的な空気圧管理を行いましょう。加えて、余分な荷物を積載しないことや不要なカスタムパーツを外すなど、車体重量を軽減する工夫も効果的です。これらの実践によって、標準的なグロムの燃費性能をさらに引き上げられる可能性があります。
2−3.燃費とツーリングの実用性
グロムはコンパクトな車体と高燃費が特徴ですが、ツーリングでの実用性を考えるときに重要なポイントがあります。まず、高燃費はロングツーリングでも給油回数を減らせるメリットがあります。例えば、燃費がリッターあたり50kmの場合、タンクが満タン(約5.7L前後)なら一度の給油で250km程度は走れる計算です。大排気量モデルほどの航続距離はありませんが、ツーリング計画を立てる際に休憩ポイントをこまめに設定すれば十分に楽しめるでしょう。
また、小排気量であるがゆえの取り回しの良さは、街中からワインディングまで幅広いシーンでストレスを軽減します。車体が軽いことから、疲労度を抑えられるという声も多く、のんびりとツーリングを楽しみたい50代以上のリターンライダーにとって大きな利点となるでしょう。さらに、__HondaGO__などの公式アプリやマップ機能を活用すれば、ガソリンスタンドの検索が容易になり、燃費を踏まえたスマートなツーリング計画が立てやすくなります。
3.燃費観点で見るホンダグロムと他車比較

3−1.グロムとスーパーカブの燃費比較
ホンダが誇る超定番モデルであるスーパーカブは、燃費効率が非常に高いことで知られています。実際、__スーパーカブ公式サイト__の資料によれば、カブの燃費はリッターあたり60km以上を記録することも珍しくありません。一方のグロムも十分に高燃費ですが、スーパーカブと比べると若干数値が落ちる傾向にあります。これはエンジン特性の違いや車両重量、さらには設計の狙いが「遊び心」にあるためとも言われています。
ただし、グロムは見た目のスポーティさやカスタム性の高さ、また走りの楽しさといった点で異なる魅力を持っています。単純に「燃費だけ」で比較するとスーパーカブの方が優勢ですが、グロムは街乗りからツーリングまで幅広く楽しめる万能感が強いモデルです。「燃費と遊び心」を両立するバイクとして、グロムを選ぶ方も多く、そこにはライダーのライフスタイルや乗り方の志向が大きく反映されているといえます。
3−2.ランキング1位の理由を探る
ホンダグロムは小排気量クラスの人気ランキングで常に上位に位置し、特にリターンライダー層からも注目を集める存在です。バイク情報誌や__大手バイク系ウェブサイト__の投票企画では、デザインの良さや取り回しの簡単さなどが高い評価を得て、燃費面でも「維持費の安さ」に直結する利点が指摘されています。グロムは通勤やちょっとした買い物にも使いやすく、それでいてウィークエンドのツーリングも楽しめる“万能感”が、多くのファンを惹きつける理由の一つです。
また、カスタムを施して個性を出しやすい点も、ランキング上位に食い込む理由と言えます。排気系や外装パーツの豊富さから、自分好みに手を加えることで愛着が増し、結果として長期間乗り続けるオーナーが多いのです。こうした「長く乗り続けるバイク=結果的にコストを抑えられる」という図式が成り立ち、グロムは人気ランキングの常連として君臨し続けています。
3−3.燃費事例から見るユーザーの声
実際にグロムを愛用するユーザーの間では、「カスタムをしても思ったほど燃費が落ちない」「街中でリッターあたり50km以上をコンスタントにキープできる」といった声が目立ちます。__みんカラ__や__X(旧Twitter)__などのSNSでの投稿を見ても、燃費に関しては概ね高評価が多く、「予想以上にガソリン代がかからないため、普段乗りから遠出まで幅広く使いやすい」という意見が多いです。
一方で、スプロケットやマフラーなどのパワー系カスタムを行うと燃費が低下する場合も報告されています。特にパワフルな走りを求める設定にすると、エンジン回転数が高めになりがちで、その分だけ燃料消費が増えるという仕組みです。そのため、「燃費優先か、走りの楽しさ優先か」をバランス良く考えながらカスタムを進めることが重要といえるでしょう。こうしたユーザーの実体験に基づく情報は、これからグロムの購入を検討するリターンライダーにも大いに参考になります。
4.タンク容量と燃費のバランス

4−1.グロムのタンク容量の特徴
グロムのタンク容量は約5.7Lと、一般的な中型以上のバイクと比べると小さめです。しかし、小排気量かつ高燃費という特性から、同クラスの他車と比較しても航続距離は決して短くありません。実際にグロムで街乗りをメインとする場合、1回の満タン給油でおよそ200〜250km程度走行できるとされており、日常的な移動には十分なキャパシティがあります。
また、タンク容量が小さいことで車体が軽量化され、取り回しの良さにも寄与しているという利点が挙げられます。重たいタンクを抱える大排気量モデルとは異なり、グロムの軽快なハンドリングは都市部でのすり抜けや取り回しにおいても優れたパフォーマンスを発揮します。こうした点が、久しぶりにバイクに戻ってきたリターンライダーが扱いやすいと感じる要因の一つになっています。
4−2.長距離ツーリングにおけるタンク容量の課題
一方、タンク容量が5.7Lと小さい点は、長距離ツーリングを計画する際に注意が必要です。燃費が良いとはいえ、リッターあたり50kmを想定しても連続で250km程度の走行が限度となります。大排気量モデルであれば、タンク容量の大きさから一度の給油で400km以上走行できる場合もあるため、休憩の取り方やルートプランニングが変わってくるでしょう。
特に高速道路を使う場合、高回転域で走り続けると燃費が低下し、タンク容量の問題が顕在化しやすくなります。給油ポイントが限られる高速区間では、あらかじめスタンドの位置を把握しておく必要があります。最近では__NEXCO公式アプリ__などで高速道路のサービスエリアやガソリンスタンド情報を確認できますが、グロムの小さなタンク容量を考慮して、こまめな給油を心がけることが安心につながります。
4−3.効率的な給油タイミングのチェック方法
グロムでロングツーリングを楽しむためには、給油タイミングをうまくコントロールすることがポイントです。まずは燃費をこまめに計測し、リッターあたりの走行距離を把握しておきましょう。最近のナビアプリや車両管理アプリには、走行距離と給油量を記録し、自動的に燃費を算出してくれる機能があります。こうしたテクノロジーを活用すれば、燃費変動の傾向をつかみやすく、余裕を持った給油計画を立てられます。
また、タンクの残量を正確に把握するために、グロムの燃料計や走行距離メーターを定期的に確認する習慣をつけると安心です。特に、高速道路や山間部などガソリンスタンドが少ない地域では、早め早めの給油がトラブル回避の鍵となります。__ツーリングクラブ公式サイト__においても、「航続可能距離を把握し、給油時期を意図的にコントロールすることで、ツーリング時の不安が軽減される」と紹介されています。
5.中古車選びと燃費の関係

5−1.燃費視点での中古車の魅力
中古のホンダグロムを選ぶメリットの一つに、価格面でのコストダウンが挙げられます。新車よりも初期購入費用を抑えられるため、その分、メンテナンス費やカスタムに回せる予算が増えるという考え方もあるでしょう。燃費性能に関しても、グロムは基本設計がしっかりしているため、大きく損なわれるケースは少ないとされています。
特に近年のモデルであれば、__PGM-FI__などの電子制御技術が搭載されているため、エンジンのコンディションさえ良好であれば極端な燃費低下は起こりにくいのが特徴です。リターンライダーにとっても、中古車市場で状態の良いグロムを見つけることができれば、コストパフォーマンスに優れた燃費性能を手に入れられるでしょう。ただし、過度なカスタムが施されている車両は、燃費が安定しない可能性があるため注意が必要です。
5−2.走行距離と燃費劣化のチェックポイント
中古のグロムを選ぶ際、まず確認すべきは走行距離とメンテナンス記録です。走行距離が増えるほどエンジン内部の摩耗が進行し、圧縮比の低下やフューエルインジェクションのトラブルなどにより燃費が悪化する恐れがあります。ただし、__ホンダディーラー__で定期的にメンテナンスを行っている車両であれば、大幅な燃費低下は起こりにくいでしょう。
チェックポイントとしては、アイドリングが安定しているか、加速時に異音や振動がないかなど、エンジンの状態を総合的に把握することが大切です。また、オイル交換やプラグ交換の履歴が残っているか確認するのも有効です。これらの履歴があれば、前オーナーがどの程度メンテナンスに気を配っていたかを推測でき、燃費性能の維持に関しても期待が持てます。
5−3.中古車レビューと実燃費の傾向
中古車サイトや__バイク情報誌__のレビューを見ると、走行距離1万km未満のグロムであれば、新車とほぼ同等の燃費を保っているケースが多いようです。また、3万km以上走行していても、オイル交換やチェーンメンテナンスを適切に行っている車両では、リッターあたり45〜50km程度の安定した数値が得られている報告があります。
一方、長期間放置されていた車両や、改造歴が複雑な車両の場合は燃費にばらつきが生じる可能性が高いです。特にキャブレター式のバイクであればジェット類のセッティングが狂いやすいですが、グロムはFIモデルが主流のため、定期的なメンテナンスを怠らなければ燃費に大きな悪影響が出にくい点はメリットと言えるでしょう。購入前に試乗ができるなら、実際の燃費を測定するか、オーナーに確認するのが一番確実です。
6.メンテナンスで向上する燃費

6−1.オイル交換と燃費への影響
エンジンオイルはエンジン内部の潤滑や冷却を担い、その状態が悪化すると燃費にも直結して影響を及ぼします。交換時期を過ぎたオイルは粘度が下がり、摩擦抵抗が増すことで燃料消費量を押し上げてしまうのです。__ホンダ純正オイル__はグロム用に最適化されており、公式には3,000〜5,000kmごと、もしくは半年ごとの交換が推奨されています。
また、質の良いオイルを使うだけでなく、適切な量を維持することも大切です。オイル量が少なすぎると潤滑不良を起こし、多すぎるとオイルシールへの負荷が増大してしまいます。交換の際は必ず規定量を守り、ゲージや窓から定期的に確認を行いましょう。リターンライダーにとっても、オイル交換は基本的なメンテナンス作業の一つですが、燃費を良好に保つためには見逃せない要素となります。
6−2.燃費改善に役立つ装備とパーツ
燃費をさらに高めたいと考える場合、タイヤの選択やチェーンのメンテナンスも重要な要素です。例えば、__ローフリクションチェーン__を採用することで駆動抵抗が下がり、わずかではありますが燃費向上が期待できます。また、転がり抵抗の少ないタイヤを選ぶことも有効です。ただし、グリップ力や耐久性とのバランスを考慮する必要があるため、自分の走行スタイルに合わせて選択しましょう。
その他にも、軽量ホイールやエンジンスライダーなど、車両重量を軽減できるパーツを導入することで燃費へのプラス効果が得られる場合があります。ただし、過度な軽量化は走行安定性を損なう恐れもあるため、カスタムパーツの選定には十分な下調べが必要です。燃費最優先のパーツ構成にしても楽しさが半減してしまうケースもあるため、バランスをとることが大切でしょう。
6−3.定期的な点検がもたらすメリット
燃費を含めた車両コンディションを最良に保つためには、定期的な点検と消耗品の交換が不可欠です。チェーンの伸びやスプロケットの摩耗は走行抵抗を増やし、燃費悪化の原因となります。加えて、ブレーキパッドやブレーキディスクに余分な引き摺りがある状態が続くと、タイヤの回転が阻害されるため要注意です。
メーカーが推奨する定期点検スケジュールや__点検パッケージ__を活用すれば、重要な部品の劣化を早期に発見でき、燃費低下やトラブルを未然に防止できます。これは、50代以上のリターンライダーにとっても安全面やコスト面で大きなメリットがあります。まめな点検と消耗品交換を行うことで、燃費を良好に保ちながら安心してバイクライフを楽しむことができるでしょう。
7.カスタムと燃費の関連性

7−1.燃費を考慮したカスタム例
ホンダグロムはカスタムパーツが豊富に存在し、外観や走行性能を自分好みに仕上げる楽しさが魅力です。しかし、燃費を重視する場合には、カスタムパーツ選びに一工夫が必要です。例えば、__ハイフローエアフィルター__に交換すると吸気効率が上がり、少しだけパワーアップが望める一方、燃費が悪化する可能性があります。一方で、軽量化パーツを導入すればバネ下重量を減らせるため、燃費改善に寄与するかもしれません。
特におすすめなのが、エンジンスライダーや軽量ステップなど、操作性の向上と重量低減を両立するカスタムです。こうしたカスタムを行うと、ライディングポジションが快適になる上に燃費も大幅に悪化しにくいというメリットがあります。カスタムを検討する際は「見た目」「走り」「燃費」の三要素をバランス良く見極めることが、長くグロムを楽しむコツといえます。
7−2.バッフル装着と燃費への影響
マフラー交換はグロムカスタムの定番ですが、排気抵抗の変化が燃費に影響する点に注意が必要です。フルエキゾーストなどに替えると、音量やパフォーマンスの向上が得られる一方、燃料の噴射マップを再設定しないと燃費が悪化する可能性があります。そこで、バッフル装着を適切に行うことで、ある程度の排気効率と燃費を両立することが可能です。
一部の社外マフラーでは、__メーカー推奨のバッフル設定__を用意している場合があり、それに従うことで燃費悪化を最小限に抑えつつ心地よい排気音を楽しめるという仕組みになっています。燃費を極力落としたくない方は、パワーチェックや空燃比の調整など専門ショップに相談するのも一つの方法でしょう。ただし、違法改造にならないよう排気音量や保安基準をしっかり確認することが大切です。
7−3.カスタム時の注意点と燃費対策
グロムのカスタムは幅広いジャンルが楽しめる一方、燃費への影響を考慮しないまま手を加えると、維持コストが想像以上にかさむケースがあります。特に、パワーアップ系カスタムは燃料噴射量を増やす方向へ調整するため、燃費低下につながりやすいです。そこで、カスタム計画を立てる際には、「燃費を重視する部品」「走りを重視する部品」を明確に仕分けすることがポイントになります。
また、カスタム後の試運転や燃費測定を行い、その結果を踏まえてセッティングを微調整することをおすすめします。__パワコマ(Power Commander)__などの燃料調整ツールを用いれば、エアクリーナーやマフラー交換後の空燃比を最適に近づけることが可能です。結果的に燃費も極端には悪化せず、快適な乗り味を得られるでしょう。こうした注意を払うことで、グロムを自分好みに仕上げつつ、長く維持できる燃費を保つことができます。
8.ホンダグロムのスペックと燃費の関係

8−1.排気量と燃費のバランス
ホンダグロムの排気量は125ccで、いわゆる原付二種カテゴリーに属します。原付二種は維持費や保険料が比較的安いだけでなく、小排気量ならではの高い燃費性能が魅力です。グロムのエンジン設計は、コンパクトながらトルクをしっかり生み出すように最適化されており、街乗りからちょっとしたツーリングまでそつなくこなせるバランスを実現しています。
これが大排気量モデルになると、排気量が増える分燃料噴射量も多くなり、燃費が低下するのは当然の流れです。しかし、グロムの場合は125ccでありながら走りの楽しさを損なわないようトルク特性が工夫されているため、実用域での加速感や軽快感を得ながらも比較的高い燃費を維持できるのです。エンジン特性と排気量のバランスがグロムの人気を支えている要因の一つといえます。
8−2.トルクと燃費効率の相関性
燃費にはエンジン出力だけでなく、トルク特性も大きく関わります。トルクが低回転域からしっかり出るエンジンほど、街中で頻繁にシフトアップダウンを行わずに走れるため、結果的に燃費が良くなるケースがあります。グロムのエンジンはボア×ストロークがコンパクトに設計されており、低中速域でのトルクが扱いやすいのが特徴です。
この扱いやすいトルク特性のおかげで、無理にエンジンを回転させなくても必要十分な加速が得られるため、燃料を大量に消費する高回転域を多用しにくいのです。さらに、__PGM-FI__の優れた燃調制御も相まって、街乗りでもリッターあたり50km前後の燃費を維持できるというわけです。トルクと燃費効率のバランスが取れたグロムは、エンジン負荷を最小限に抑えながら楽しめるバイクと言えます。
8−3.エンジン技術で見る燃費性能
ホンダグロムのエンジンには、先進的な技術が数多く盛り込まれています。シリンダー内部の摩擦抵抗を抑えるための特殊コーティングや、燃焼効率を高める燃焼室設計など、__ホンダ独自の低燃費技術__が数多く投入されています。これにより、従来のキャブレター車と比較しても、アクセル操作に対するレスポンスが良いだけでなく、燃料の無駄遣いを最小限に抑える仕組みが実現されているのです。
また、近年の環境規制に対応するため、エンジン排気ガスのクリーン化も重要視されています。三元触媒や酸素センサーなどの補機類が最適に働き、排気ガスを適切に浄化すると同時に燃費悪化を防ぐ工夫がなされています。こうした技術の積み重ねが、グロムの「遊び心」と「燃費性能」を両立する大きな原動力となっています。
9.新車と中古車の燃費性能比較

9−1.燃費の観点で見る新車のメリット
新車のグロムを選ぶ最大のメリットは、最新のエンジン制御技術やフレーム設計が採用されていることです。特に2023年以降のモデルでは、より厳しい排ガス規制をクリアするために燃調が最適化されており、初期のグロムと比べるとさらに燃費が向上しているケースがあります。__2024年6月更新のホンダ公式資料__によれば、一部のユーザー実測値でリッターあたり55〜60kmを記録する事例も報告されています。
さらに、新車を購入することで保証が受けられたり、初回点検や定期メンテナンスのプランがセットになっていることも多く、コンディション維持にかける手間が少なくて済むのも魅力です。やや車両価格は高めになりますが、燃費の良さとメンテナンス費の軽減によって長期的に見ればコストメリットを得られる可能性があります。
9−2.中古車燃費が劣化する条件とは
中古車の燃費が劣化する主な原因は、エンジンや駆動系パーツの摩耗、そしてメンテナンス不足です。エンジンの圧縮漏れやインジェクターの目詰まり、オイルシールの劣化などが進行すると、設計時の燃費性能を発揮できなくなってしまいます。走行距離が多い車両や、定期的なメンテナンスを受けていない車両では、燃費が大きく落ち込んでいるケースも珍しくありません。
また、長い間放置されていたり、過激なカスタムが施されていると、セッティングのズレや燃料噴射量の乱れが生じることもあります。__整備不良車__を購入した場合、後からパーツ交換や調整にコストをかける必要が出てくるため、最終的には新車同等以上の出費になるリスクも考えられます。中古車選びでは、事前の情報収集と試乗、整備記録の確認が重要となるでしょう。
9−3.登録年式別の燃費パフォーマンスランキング
グロムは発売以降、細かな改良やモデルチェンジを重ねてきました。初期モデル(2013年〜)から2020年頃までのモデルでは、大きな燃費差はないものの、細部のエンジンマネジメントが年式ごとに若干異なるため、年式が新しいほど総合的に燃費が良い傾向にあります。__バイク専門メディア__のデータ集計では、2022年以降のモデルがリッターあたり53km前後の実測値を示すことが多いと報告されています。
ただし、燃費性能の差異はオーナーの乗り方や環境、カスタム状況によっても左右されます。そのため、必ずしも最新モデルが絶対に一番燃費が良いとは限りません。年式別のランキングは参考情報として見るにとどめ、最終的には実車の状態や試乗感を重視する方が賢明でしょう。いずれにせよ、モデルチェンジを重ねるごとにエンジンの制御や環境性能は向上しているため、新しめのグロムほど燃費面のアドバンテージがあると考えられます。
10.実際のレビューでわかる燃費事情

10−1.ブログや動画レビューの燃費情報
最近では__YouTube__や__個人ブログ__など、多くのメディアでグロムの燃費や維持費に関するレビューが公開されています。例えば、「街中メインで乗るとリッターあたり50km前後」「郊外の下道を一定速度で走ると55km近くまで伸びる」といった具体的な数値を挙げているケースが多く、実際のオーナーが発信する生の声は信頼度が高いです。
動画レビューでは、実際に給油から走行距離を計測して燃費を公開している例もあり、よりリアルな情報を得やすくなっています。また、天候や乗り方の違いによる燃費変動をわかりやすく示しているチャンネルもあるため、リターンライダーが自分のライフスタイルに合わせて燃費をイメージしやすいのも利点です。こうした情報を総合的にチェックすると、グロムの燃費性能がいかに安定しているかが見えてきます。
10−2.みんカラでの燃費に関する投稿者の回答
__みんカラ__は四輪車のイメージが強いですが、実はバイクに関しても多くのユーザーが登録し、燃費データやカスタム情報を共有しています。そこでは「冬場は暖気の関係で燃費が落ちるが、それでもリッターあたり45kmは切らない」「夏場のロングツーリングでは驚くほど燃費が伸びる」など、具体的なシーズン別の燃費変動が詳しく投稿されています。
また、カスタム状況を公開しているユーザーの中には、「マフラー交換後に燃費が2〜3km/Lほど下がったが、パワーアップのメリットを考えると許容範囲」というリアルな声も見受けられます。こうした実際のオーナーの生データは、メーカー公表値とは異なる乗り手目線の情報であり、グロムを検討している方にとっては非常に参考になるでしょう。
10−3.燃費不満点と解決の口コミ事例
ユーザーの声を見ていると、中には「もう少し燃料タンクが大きければ、給油回数を減らせるのに」という意見や下道中心のルートに変えたら燃費が改善した」などのコメントが口コミとして寄せられています。要するに、グロムの特性に合わせた走り方やプランを工夫すれば、多くの不満点を解消できるというわけです。リターンライダーにとっても、無理なく乗り続けられる環境を整えることで、燃費面のメリットを最大限に活かすことができます。
11.私の体験談
SNSでは50代で子育てが一段落したタイミングでグロムに乗り始めたリターンライダーの記事から、先日、__Instagram__で出会った同世代のバイク仲間が投稿していた写真に「燃費の良さのおかげで、夫婦でのツーリングを気軽に計画できる」というコメントもあり共感できます。彼は九州の山間部をグロム2台で走り回っているそうで、1泊2日の小旅行でも1人あたりのガソリン代は2,000円以下に収まると語っています。
また、__X(旧Twitter)__でやり取りしている別のオーナーは、普段は街乗り中心でリッターあたり50km程度をキープしながら、休日には下道を使ったロングツーリングを楽しんでいるそうです。「大排気量モデルと比べるとパワーは劣るけど、燃費が良いので長期的なコスト負担が軽く、思う存分走り回れる」という声は、多くのリターンライダーが目指すライフスタイルにぴったりではないでしょうか。
12.燃費観点で考えるホンダグロムの魅力と長期使用でのコスト効果 まとめ
ホンダグロムは125ccという小排気量ながら、燃費性能に優れ、街乗りからツーリングまで幅広く対応できる万能感が魅力のバイクです。燃費が良いことで維持費が抑えられ、結果として長期間乗り続けやすいというメリットがあります。今回紹介した各大見出しでは、グロムの燃費データや他車との比較、タンク容量の課題、中古車選びのポイント、メンテナンスやカスタムの影響など、多角的に「燃費」と「コスト効果」を検証しました。
リターンライダーとして再びバイクライフを始める50代以上の方にとって、グロムは扱いやすく維持もしやすい最適な選択肢と言えます。カスタムにこだわりながらも燃費を重視する方、長距離ツーリングの計画を立てる方、そして中古車でコストを抑えたい方など、あらゆる目的に応じて幅広く応えてくれる懐の深さがグロムの大きな魅力です。ぜひこの情報を参考に、自分らしいバイクライフを楽しんでみてください。