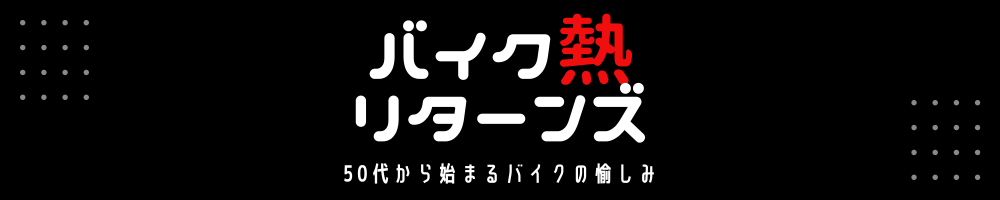(本ページにはプロモーションが含まれています)
1.イントロダクション
ゴールドウィングとハーレーはいずれも大型バイクの代名詞であり、その所有感や乗り心地はライダーを強く魅了します。しかし、実際にどちらを選ぶべきかは迷うところ。価格やデザイン、メンテナンス性など、気になる要素も多く、後悔につながる可能性もあります。本記事では、それぞれの特徴を比較しながら、バイクリターンを考える50代以上の方が抱く疑問点を解決し、後悔しない選択へと導きます。
2.ゴールドウイングとハーレー、どちらを選ぶべきか徹底比較

2-1.ゴールドウイングとハーレーの基本性能比較
大型クルーザーを代表するゴールドウィングとハーレーは、どちらも長距離を快適に走れるツーリング性能を備えています。しかし、それぞれのエンジン特性や車重、乗り味には大きな違いがあります。たとえば、ゴールドウィングは水平対向エンジンを搭載しており、振動が少なく安定感に優れています。ホンダの公式情報では「ゴールドウィングの水平対向エンジンは重心が低く、高速走行時の安定性を高めている」とされています(参考:ホンダ公式サイト)。一方で、ハーレーは伝統的なVツインエンジンを採用しており、鼓動感やエンジンサウンドの迫力が魅力です。独特の振動を「味」と感じるライダーも多く、アメリカンスタイルを存分に楽しめるのが特徴でしょう。
また、車重に関してはゴールドウィングの方がやや重めですが、低重心設計のおかげで実際の取り回しは想像以上に楽という声があります。ハーレーはモデルによって車重が大きく異なるため、自分に合ったモデル選びが重要です。このように、エンジン特性と車重のバランスが大きく異なるため、実際に試乗をして乗り比べることが後悔を防ぐ第一歩となります。
2-2.ツーリングに最適なのはどっち?
長距離ツーリングを前提にバイクを選ぶ場合、シートの快適性や積載性、風防(ウインドシールド)の性能が大きな比較ポイントとなります。ゴールドウィングは大型のウインドスクリーンに加え、豪華なシート、そしてしっかりとしたパニアケースやトップケースを標準装備していることが多く、まさに「走る高級サルーン」と呼ばれるほど快適装備が充実しています。「ゴールドウィングのシートは長時間座っても疲れにくい」というオーナーの声も多く、実際にロングツーリングを重ねるほど、その恩恵を感じられるでしょう。
一方でハーレーにも、多彩なツーリングモデルが用意されています。ウインドシールドやサドルバッグ、トップケースなどを装備したモデルであれば、ロングツーリングに必要な積載能力も十分確保できます。ただし、ゴールドウィングと比べると、標準での装備がやや簡素に感じるかもしれません。そのため、ハーレーの場合はカスタムパーツを追加して自分好みに仕上げる楽しみがある一方、カスタム費用がかさむ可能性があります。どちらが“最適”かは、求める快適性やカスタムの自由度をどう評価するかによって大きく変わるでしょう。
2-3.人気モデルの違いを解説
ゴールドウィングの人気モデルとしては、現行型の「GL1800シリーズ」が挙げられます。軽量化を進めながらも、電動式ウインドスクリーンやApple CarPlay対応など先進的な装備を備え、長期ツーリングのみならず日常的な使い勝手も向上している点が評価されています。「最新のゴールドウィングは、車体が軽く取り回しが格段に良くなった」というオーナーの口コミ(参考:バイク専門SNS)もあり、従来のイメージを覆す魅力を打ち出しています。
ハーレーの人気モデルとしては「ツーリングファミリー」に属するロードグライドやウルトラリミテッドなどが有名です。大型のフェアリングと快適なシートを標準装備し、高速道路でも安定したクルージングができると評判です。また、カスタムの幅が非常に広く、見た目も機能も自分流に仕上げられる点がハーレーならではの魅力といえます。どちらのバイクもモデルラインナップが豊富にあるため、まずは自分が重視するポイント(デザイン、積載、先進装備など)を整理してから候補を絞り込むと、より満足度の高い選択につながります。
3.ゴールドウィングの良さと欠点を検証

3-1.ゴールドウィングの快適装備と乗り心地
ゴールドウィングを語るうえで外せないのが、その充実した快適装備です。大型ウインドスクリーンとフェアリングにより、風を効果的に防いでくれるだけでなく、足元のエンジン熱がライダーに直接伝わりにくい設計になっているため、快適に長距離を走破できます。さらに、シートの形状やクッション性も考え抜かれており「まるでソファーに座っているようだ」というオーナーの声も多いです。
また、オーディオシステムやグリップヒーター、場合によってはエアバッグ搭載モデルなど、他のバイクにはない装備が豊富に用意されています。こういった先進機能のおかげで、安全かつ快適にロングツーリングを楽しめるのがゴールドウィングの大きな魅力です。しかし、その分バイク全体のメカニズムが複雑化しており、いざ修理が必要になったときに費用や時間がかかるリスクも否めません。快適性と先進装備の恩恵をとるか、シンプルな構造を好むかは、ライダーの価値観に大きく依存するといえるでしょう。
3-2.ゴールドウィングの欠点と後悔ポイント
「大きい」「重い」というゴールドウィングの固定イメージは、実際には最新モデルでかなり改善されています。しかし、それでもなお車体サイズは一般的な大型バイクよりも大きく、取り回しのハードルを感じる人は少なくありません。特に街中や細い路地、駐車場でのUターンなどでは、重量とホイールベースの長さがストレスになる場合もあります。また、純正パーツや整備費用が高めになりやすいため、メンテナンスコストの高さを後悔するケースもあるでしょう。
さらに、豪華装備ゆえにトラブルが起こった場合の修理費が高額になる可能性があります。電子制御系のトラブルは専門知識を要するため、カスタムやDIY整備を好む人にとっては物足りなさを感じるかもしれません。「トラブルが起きたときの修理代が高すぎて後悔した」という意見(参考:バイク整備フォーラム)も散見されます。とはいえ、ゴールドウィングが持つ圧倒的な快適性と長距離性能は他に代えがたい価値でもあるため、一長一短を理解して購入を検討することが重要です。
3-3.ゴールドウィングの操作性と特長
ゴールドウィングは、低重心設計と最新の電子制御が組み合わさることで、実際に乗ると思いのほか扱いやすいと感じるライダーが多いバイクです。オートマチックトランスミッション(DCT)搭載モデルもあり、クラッチ操作が不要になるため渋滞時のストレスを大幅に軽減してくれます。特に「DCTのゴールドウィングは都市部での取り回しが予想以上に楽」といった声(参考:ライダーズコミュニティ参考)は少なくありません。
また、高速道路やワインディングでの走行安定性は折り紙付きで、直進時はもちろん、コーナリング時の安定感にも定評があります。その一方で、押し歩きが多い場面や、急坂での取り回しにはやはり注意が必要です。重量や大きさを把握して、安全にバイクをコントロールするための慣れが求められます。こうした特長を「ツアラーとして最高」と感じるか「街乗りには扱いづらい」と感じるかは、ライダーの使用シーンや経験値によって変わってくるでしょう。
4.ハーレーの魅力と気になるデメリット

4-1.ハーレー特有のスタイルとデザイン
ハーレーといえば、やはりその独特のスタイルと存在感が最大の魅力でしょう。クラシカルなヘッドライトや大型のフューエルタンク、Vツインエンジンが織りなす迫力あるシルエットは、多くのライダーを虜にしてきました。「ハーレーは見るだけでテンションが上がる」という声は珍しくなく、愛車を眺める時間が長くなるのもハーレーオーナーの特徴かもしれません。
また、カスタムパーツの豊富さもハーレーならでは。社外パーツメーカーが数多く存在し、ハンドルやマフラー、シートなど、ライダーの好みに合わせて徹底的にカスタムが楽しめます。この自由度の高さは「自分だけの一台を作り上げたい」というカスタム愛好家にとって、ハーレーが特別な存在である理由のひとつです。ただし、純正および社外パーツともに高価な傾向があるため、費用面で苦労するケースもあるかもしれません。
4-2.ハーレーを選ぶ際の注意点
ハーレーは様々なモデルがラインナップされており、それぞれの車重や足つき、エンジン特性が大きく異なります。初心者やリターンライダーにとっては、まず自分の体格や乗り方に合ったモデルを見極めることが重要です。足つきに関して「ハーレーはシート高が低めと言われるが、モデルによって大きく違う」との意見(参考:バイク関連ブログ)もあるため、実際に複数のモデルに跨がって確認することをおすすめします。
また、ハーレーの多くは空冷エンジンを採用しているため、気温が高い季節や渋滞での熱対策が課題になることがあります。エンジンオイルやプラグの交換サイクルにも気を配り、定期的なメンテナンスが必要です。さらに、ハーレー特有の鼓動感は魅力ですが、振動対策としてパーツの増し締めやゴムブッシュの点検なども欠かせません。こうしたメンテナンスを楽しめるかどうかが、ハーレーを選ぶうえでの重要なポイントといえるでしょう。
4-3.ツーリング性能で気になる点
ハーレー=アメリカンのイメージから、長距離をまったりとクルージングするのが得意、という印象を持つ方も多いでしょう。実際、ウインドシールドやサドルバッグを装備したツーリング系モデルは、高速巡航に適したセッティングがなされています。ただし、純正のウインドプロテクションがゴールドウィングほど充実していないケースがあり、オプションで大きめのフェアリングを装着するオーナーも少なくありません。
また、サスペンションのセッティングは硬めのモデルが多い傾向にあり、路面の段差を拾いやすい場合があります。「ロングツーリングで腰に負担がかかる」という意見(参考:ハーレーオーナーズグループ)もあるため、自分に合ったシートやサスペンションにカスタムするなど工夫が必要です。こうした微調整やカスタムは面倒な部分もありますが、その一方でハーレーには“育てる楽しみ”があり、乗り込むほどに愛着が増していくのも大きな魅力といえるでしょう。
5.ゴールドウイングはダサい?デザインの評価

5-1.ゴールドウィングの見た目に対する意見
ゴールドウィングはその大型のカウルとボリューミーな車体デザインから「ダサい」と言われることも少なくありません。しかし、実際には「ラグジュアリー感があって威圧的なまでの迫力がむしろかっこいい」と評価する声も多く、好みが大きく分かれるポイントといえます。新しいモデルではスポーティなラインが取り入れられ、従来の重厚感を保ちつつ洗練されたシルエットへと進化しています。
一方、海外のバイクメディアでは「ゴールドウィングは大型クルーザーの王様」と称されることもあり、アメリカでも根強い人気があります。見た目の好みは個人差が大きいものの、「乗ったらわかる」「見た目より取り回しが楽で驚く」という意見が多いのも事実です。実車を見る機会があれば、細部の仕上げや質感にも注目すると、ゴールドウィングのデザインの魅力を再発見できるかもしれません。
5-2.ハーレーとのデザイン比較
ハーレーは伝統的なアメリカンスタイルを守りつつ、多様なモデル展開でライダーのニーズに応えてきました。そのため、ハーレーのデザインは一目で“ハーレーらしさ”がわかる独自の個性を放っています。対してゴールドウィングは、初代モデルから続く「フルカウル・大型収納・豪華装備」というコンセプトを踏襲しつつ、時代に合わせて先進的な要素を取り入れてきました。
見た目だけで言えば、ハーレーが「男らしく無骨なスタイル」、ゴールドウィングが「豪華絢爛なツアラーデザイン」という印象を抱く人が多いでしょう。ハーレーの場合はアフターパーツで雰囲気をガラリと変えられる余地が大きいのに対し、ゴールドウィングは車体カウルの設計がしっかりしている分、外見のカスタムの自由度はやや少なめです。どちらも一長一短があり、「自分らしさ」を追求したいならハーレー、「最初から完成度の高い外観を求めるならゴールドウィング」と捉えるとわかりやすいかもしれません。
5-3.長距離走行で目立つデザインの良し悪し
長距離ツーリングとなると、デザインは単なる見た目だけでなく、機能美も重要になってきます。ゴールドウィングの大型カウルは、風防効果だけでなくエンジン熱の逃がし方にも工夫が凝らされており、「夏の長距離でも比較的涼しく走れる」との評価があります。一方、ハーレーのカスタムフェアリングは自分の好みに合わせやすい半面、風防効果が純正と比べて劣るパーツもあるため、選択には注意が必要です。
また、ゴールドウィングのLEDライトや計器類などは視認性の高さが評価される一方、ハーレーでも「デイメーカーLEDヘッドライト」など先進装備を取り入れているモデルがあります。長距離を走るほど「見た目のスタイル」だけでなく、「どれだけ疲れにくいか」「安全に走れるか」という点がデザインにも影響してくるでしょう。それぞれのバイクが持つ機能美を理解し、ロングツーリングでも快適に走行できる装備を重視することが、後悔を減らすコツです。
6.ゴールドウィングの寿命と中古市場の評価

6-1.ゴールドウィングの寿命に関する評判
ゴールドウィングは、もともとホンダの技術力を結集したフラッグシップモデルと位置づけられています。その信頼性は高く、適切なメンテナンスを施せば10万km以上走行しても「まだまだ余裕がある」と言われるほどのエンジン寿命を持つケースも珍しくありません。実際、海外の長距離ツアラーからは「ゴールドウィングは30万マイル(約48万km)走行可能」といった話もあるほどです(参考:海外バイクフォーラム)。
ただし、電子制御系や複雑な装備を多用しているため、一部のパーツが故障した場合は高額修理となることもあります。エアバッグ搭載モデルやDCTモデルなどは構造がより複雑なので、トラブルが発生した際の修理対応に時間がかかる可能性がある点は留意しておきたいところです。いずれにせよ、日頃からオイル交換や点検をしっかりと行うことで、ゴールドウィングのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。
6-2.中古ゴールドウィングを選ぶ際の注意点
中古市場でゴールドウィングを探す際は、まず年式と走行距離だけで判断しないことがポイントです。メンテナンス履歴がしっかり残っている個体や、ディーラー系ショップで定期点検を受けてきた個体であれば、走行距離が多くても安心感は高いでしょう。特にゴールドウィングはフルカウル構造のため、外装の割れやクラック、転倒歴の有無などをよく確認することが大切です。
また、電子制御系が多い近年のモデルでは、故障診断機を使ったチェックやテスト走行で異常がないかを確かめる必要があります。「中古で格安だったけど電装系トラブルに悩まされて結局高くついた」という体験談(参考:バイク購入ブログ)もあるように、最初の購入費用だけでなく修理コストも視野に入れて検討しましょう。長く乗り続けるためには、購入後の整備や保証体制も含めて総合的に判断することが後悔を防ぐカギです。
6-3.ハーレーとの寿命比較
ハーレーもまた頑丈なエンジン設計で知られており、こまめなオイル交換や点検を続ければ10万km以上走行可能な個体も少なくありません。構造が比較的シンプルな分、DIYでのメンテナンスがしやすいのもハーレーの特徴です。「自分でエンジン周りをいじりながら長く乗るのが楽しい」というハーレーオーナーも多く、愛着を持って付き合えるバイクといえます。
一方、ゴールドウィングは電子制御技術に強みを持つホンダが手掛ける高耐久モデルですが、トラブルが起きた際に専門的な知識や設備が必要になるケースも多いです。したがって、DIY整備よりもディーラーや専門ショップに依存しがちという声があります。どちらも基本的な寿命は長いものの、いざトラブルが生じたときに対応しやすいのはハーレー、先進機能による快適性を得やすいのはゴールドウィング、といった住み分けがあるでしょう。
7.ゴールドウィングの立ちゴケ防止技術と安定性

7-1.ゴールドウィングが倒れない仕組みとは?
近年のゴールドウィングでは、重心を下げる設計に加えて、車体を立てたまま低速で移動する際の安定性に配慮した技術が採用されています。たとえば、停止寸前にエンジンのトルク制御を微調整し、スムーズに足を出せるように工夫されているなど、乗り手の操作をサポートする仕組みが数多く組み込まれています。「以前のモデルと比べて、立ちゴケしにくさが格段に向上している」というオーナーの意見(参考:ゴールドウィング愛好会)もあり、重量級バイクにありがちな不安要素を軽減する取り組みが進んでいます。
また、DCTモデルでは、クラッチ操作ミスによる急発進やエンストが起きづらいため、慣れない状況でも比較的安定して発進・停止を行いやすいです。ただし、重心が低いとはいえ車重は300kgを超えるため、前後左右に車体を振るようなシチュエーションでは注意が必要。完璧に「倒れない」わけではなく、あくまでライダーの慎重な操作と相まってこそ成立する技術といえるでしょう。
7-2.立ちゴケ防止技術が選ばれる理由
大型バイクの立ちゴケは、ライダーにとって大きな精神的ダメージだけでなく、車体に傷や破損を負わせる原因にもなります。ゴールドウィングのように高価なフルカウル車の場合、立ちゴケでカウルにダメージを与えると修理費が高額になることも少なくありません。そうしたリスクを最小限に抑える技術は、安心してロングツーリングを楽しみたいライダーにとって非常に魅力的です。
また、ゴールドウィングに搭載されている低速時のエンジントルク制御やDCTのような先進機能は、リターンライダーや比較的年齢を重ねたライダーに人気が高い傾向があります。「昔より体力が落ちているから、少しでも安定感のあるバイクを選びたい」という声(参考:リターンライダー談話)があるように、より安全・快適に大型バイクを扱える技術は今後ますます注目されるでしょう。
7-3.ハーレーとの転倒対策の違い
ハーレーでも、エンジンガードやサドルバッグガードといった物理的なプロテクションパーツが充実しており、低速時の転倒リスクを軽減する手段があります。純正オプションとしても装備できるモデルが多く、立ちゴケの際のダメージを最小限に抑えることは可能です。ただし、ゴールドウィングのように電子制御を駆使して転倒を防止する技術は現状あまり搭載されていません。
また、ハーレー独特の車体バランスや低いシート高は、足つきの良さという面で立ちゴケリスクを下げているとも言えます。そのため、「ハーレーの方が取り回しやすい」と感じる人もいますが、これは体格やライディングスキルによって異なります。電子制御でサポートするゴールドウィングか、物理的ガードや低シート高で対応するハーレーか。どちらのアプローチが自分に合っているか、試乗や実車確認を通じて見極めることが重要です。
8.ゴールドウィングとハーレーの最高速とパワー

8-1.ゴールドウィングの最高速を試す
ゴールドウィングのエンジン排気量は1800cc前後が主流で、そのパワーは高速走行時にも十分過ぎるほど余裕があります。実際にサーキットやクローズドコースでテストを行った映像を見ると、「メーター読みで200km/hオーバーも難なくこなす」といった報告(参考:海外バイク動画共有サイト)もあります。しかし、公道でその最高速を出す機会はまずないため、むしろ余裕のあるトルクとスムーズな加速を楽しむのがゴールドウィングの真骨頂と言えるでしょう。
また、高速域でも安定性が高く、強風や後方からの風圧にも車体がブレにくい設計になっています。これは重厚な車体とフェアリング形状のおかげで、長距離移動を快適にこなすためのコンセプトが随所に活かされています。最高速を出す場面そのものは限られますが、いざというときにパワーの余裕があることは、高速道路での追い越しなど日常的なシーンでも安心感につながるでしょう。
8-2.ハーレーとの速度性能の比較
ハーレーのエンジン排気量はモデルによって異なり、ミドルクラスの883ccからツーリングモデルの1800cc超まで幅広く展開しています。ただし、ハーレーはゴールドウィングと違って、高速巡航よりも低回転域のトルクと鼓動感を重視したエンジン設計が特徴です。そのため、公道レベルの巡航速度域では十分なパワーを発揮しますが、最高速に関してはゴールドウィングほどの伸びを追求していないモデルも少なくありません。
「ハーレーは法定速度内でのゆったり巡航が気持ちいい」というオーナーの声(参考:ハーレーコミュニティ)が示すとおり、速度性能というよりはトルクを使った加速感や音の心地よさが重視されています。もちろん、大排気量モデルであれば高速道路の追い越しも楽にこなせますが、ゴールドウィングと比較すると最高速や絶対的な馬力を求めるバイクではないと言えるでしょう。
8-3.ツーリング時の実用的な速度とは?
実際に日本国内でツーリングを行う場合、高速道路での法定速度は最大120km/h(一部区間)に設定されているものの、一般的には100km/h前後の巡航がメインとなるでしょう。この速度域であれば、ゴールドウィングもハーレーもパワーに余裕があり、車体の安定性も高いです。むしろ重要なのは、長時間乗っていて疲れにくいポジションとシート、快適性を保つ防風性能などでしょう。
「実用的な巡航速度域でストレスなく走れるかどうか」が、ツーリングライダーにとっての真の性能比較ポイントです。ゴールドウィングは重厚な安定感と風防性能が秀逸で、高速域でも疲労が少ないとされ、一方のハーレーは鼓動感や乗る楽しさがありつつ、自分好みにカスタムして快適性を高めることができます。最高速や馬力という数値以上に、自分のツーリングスタイルに合ったバイクを選ぶことが後悔を減らす秘訣でしょう。
9.ゴールドウィングとハーレーのレンタル体験談

9-1.レンタルで試すゴールドウィングの感想
ゴールドウィングは価格が高額なこともあり、まずはレンタルバイクで試乗してから購入を検討する人が増えています。実際にレンタルを利用した人からは、「思ったよりも足つきが良く、街乗りでも扱いやすかった」という声や「DCTのおかげで渋滞時のクラッチ操作が楽だった」という好意的な意見が多く見られます。特に長距離ツーリングを想定している場合、実際に高速道路やワインディングを走ってみることで、ゴールドウィングの本領をしっかり体感できるでしょう。
ただし、レンタルバイクのシート高やカスタム状態は標準的な仕様であることが多いため、購入後に自分好みにカスタムする余地は残ります。逆に言えば、純正状態の快適性能を知ることで、追加でどのようなパーツを付けるかの判断材料にもなるでしょう。レンタル費用は決して安くはありませんが、後悔の少ない選択をするための試乗体験としては十分な価値があるはずです。
9-2.ハーレーのレンタル体験レポート
ハーレーにも多くのレンタルプランが存在し、スポーツスターからツーリングモデルまで幅広く選ぶことができます。実際にレンタルを利用したライダーのSNS投稿を見ると、「初めてのハーレーで鼓動感に感動した」や「振動が想像以上で腕が疲れたけど、それが楽しかった」など、良くも悪くも“ハーレーらしさ”を体験した声が寄せられています。
また、ハーレーの場合、モデルによって車体の重さや足つきが大きく異なるため、複数モデルをレンタルで乗り比べる人も少なくありません。レンタルバイクショップによってはヘルメットやジャケットなどの装備も合わせて借りられることがあるので、荷物を減らして気軽に体験できるのもメリットです。「ツアラーモデルを借りて、高速道路と下道をまんべんなく走ると、ハーレーの良さがよくわかった」という投稿もあり、走るシチュエーションを選んでレンタルすることも大切です。
9-3.レンタル利用のメリットと注意点
レンタルを利用すれば、高額な車体を買わずとも、実際のライディング感覚を掴めるのが最大のメリットです。特に大型バイクは試乗の時間が限られているケースが多いため、数時間〜数日間のレンタルでリアルな使用感を確認できるのは大きな魅力でしょう。また、複数車種を連続して乗り比べることで、自分に合ったバイクが客観的に見えてくるというメリットもあります。
ただし、レンタル料や保険料はそれなりにかかるため、短期間で何度も乗り比べると費用がかさんでしまいます。また、レンタル車両には装着制限がある場合が多く、カスタムパーツを試せないケースもある点に注意が必要です。「購入前に徹底的にレンタルで検証できて満足」という人もいれば、「何度も借りているうちに購入費用に近づいてしまった」といった声もあります。自分の予算や目的に合わせて、上手にレンタルを活用することが大切です。
10.ゴールドウィングの最新モデルとホンダの技術

10-1.ゴールドウィングの最新モデルをチェック
2024年以降の最新ゴールドウィングでは、さらなる軽量化やサスペンションの改良、そして電子制御デバイスの強化が図られています。「2024年モデルでは、車体剛性とサスペンションのセッティングが見直され、コーナリング性能が向上した」という情報(参考:ホンダ公式リリース)もあるように、ラグジュアリーツアラーでありながらスポーティな走りを楽しめる方向へ進化し続けているのが大きな特徴です。
また、スマートフォンとの連携機能や大型のTFTメーターが採用されるなど、インフォテインメント面も進化が著しいとされています。長距離を快適に移動するための装備はもちろん、ツーリング先での情報収集やナビゲーション、エンターテイメントをより直感的に操作できるよう工夫されているのは嬉しいポイントです。これらの先進機能を活かすには、定期的なソフトウェアアップデートや正規ディーラーでの点検も欠かせないでしょう。
10-2.ホンダだからこその安心感と技術力
ホンダは世界的にも大手のバイクメーカーとして、信頼性と技術力に定評があります。モトGPやさまざまなレースシーンで培ったノウハウを市販車にフィードバックする文化が根付いており、ゴールドウィングにもその精神が反映されています。「ホンダのバイクは壊れにくい」という一般的なイメージもあり、実際、消耗品の交換サイクルや故障率の低さなどでユーザー満足度が高い傾向にあるようです。
一方で、最新の電子制御技術を多く搭載しているゴールドウィングは、整備の専門知識や専用診断装置が必要になるケースが増えてきました。しかし、それは裏を返せば、全国に整備ネットワークを展開するホンダ正規ディーラーやサービスショップで手厚いサポートが受けられるということでもあります。アフターサービスの充実ぶりは、ハーレーにも劣らない大きな強みといえるでしょう。
10-3.ハーレーの最新モデルとの比較
ハーレーも近年は水冷エンジンを搭載した“Revolution Max”シリーズを展開するなど、伝統的なスタイルを守りながら技術革新を進めています。しかし、ゴールドウィングほど電子制御を前面に打ち出しているモデルは少なく、ハーレーはあくまでも“走りの味”や“カスタムの自由度”を重視している印象が強いです。
また、メーカーの整備ネットワークはハーレーも国内に数多く存在するものの、純正パーツの供給や専門的なメカニックの配置など、総合的なサポート体制はホンダの方がやや手厚いと感じるユーザーもいます。「ハーレーはカスタムを含めて自分でなんとかする楽しみがある」というオーナーの声に対し、「ゴールドウィングはメーカーの技術力とサービスに裏打ちされた安心感がある」という意見があるなど、両者のスタンスははっきりと分かれている印象です。
11.私の体験談

筆者自身は、長年ハーレーに憧れていましたが、50代に差しかかった今、ロングツーリングを重視するライディングスタイルに変わり、ゴールドウィングが気になり出した一人です。実はInstagramで見つけた「#ゴールドウィング」というハッシュタグの投稿をきっかけに、最新モデルの快適性に興味を持ちました。そこには、「東京から九州までの往復3000kmを難なく走破。腰が全然痛くならなかった」という驚きのコメントがいくつもあり、「そんなに快適なのか?」と半信半疑ながらレンタルで試乗してみたのです。
実際に乗ってみると、街中での取り回しは確かに車体の大きさを感じますが、高速巡航ではまるで高級車のようにストレスなく走れるのに驚きました。DCTモデルだったため、渋滞でのクラッチ操作から解放されるのも大きなポイントでした。X(旧Twitter)でも同様の体験談が多数あり、「もうクラッチ操作には戻れない」という人もいるほどです。かつての自分は「ハーレーこそ至高」と思っていましたが、実際に自分のライフスタイルや身体的な負担を考えると、ゴールドウィングの方が合っているかも。
もちろんハーレーにはハーレーの良さがあり、あの鼓動感やスタイル、文化が好きで乗り続ける仲間もたくさんいます。しかし、50代を超えた今、長距離をいかに快適に走れるか、メンテナンスの手間をどう考えるかを天秤にかけると、ゴールドウィングがベターな選択かも?と考えてしまいます。だからといって未練がないわけではなく、「あの独特な鼓動感をもう味わえないのはちょっと寂しい」という気持ちも正直あります。いずれにしても、実際に乗って確かめることが後悔を最小限にする近道だと感じています。
12.ゴールドウィングとハーレーを比較してわかる後悔のポイント まとめ
本記事では、ゴールドウィングとハーレーを比較しながら、どちらを選ぶべきか、そして後悔を最小限にするためのポイントを検証してきました。大きくまとめると、以下のようになります。
- ゴールドウィングの特徴
- 水平対向エンジンやDCTによる圧倒的な安定感と快適装備
- 高い初期投資と複雑な電子制御ゆえの修理・メンテナンスコストに注意
- 長距離ツーリングをメインに考える50代以上のリターンライダーには魅力的
- ハーレーの魅力
- 伝統的なVツインエンジンの鼓動感とカスタムの自由度
- メンテナンスやカスタムを自分で楽しみたい派にはぴったり
- 走りの味わいや独特の文化を求めるなら、選んで損はない
- 後悔しないためのアドバイス
- まずはレンタルや試乗を活用し、実際の乗り心地や取り回しをチェック
- メンテナンス費用やアフターサポート体制を含めて総合的に判断する
- 自分のライフスタイルと身体的負担を考慮し、長く乗り続けられるかを見極める
年齢を重ねたからこそ味わえるバイクライフは、若い頃のそれとはまた違った楽しさがあります。豪華装備で快適性を追求するか、鼓動感とスタイルでバイクの醍醐味を味わうか。いずれにしても、しっかりと情報収集と試乗を行い、自分自身が納得できる選択をすることが重要です。ぜひ参考にしていただき、後悔のないバイクライフを満喫してください。